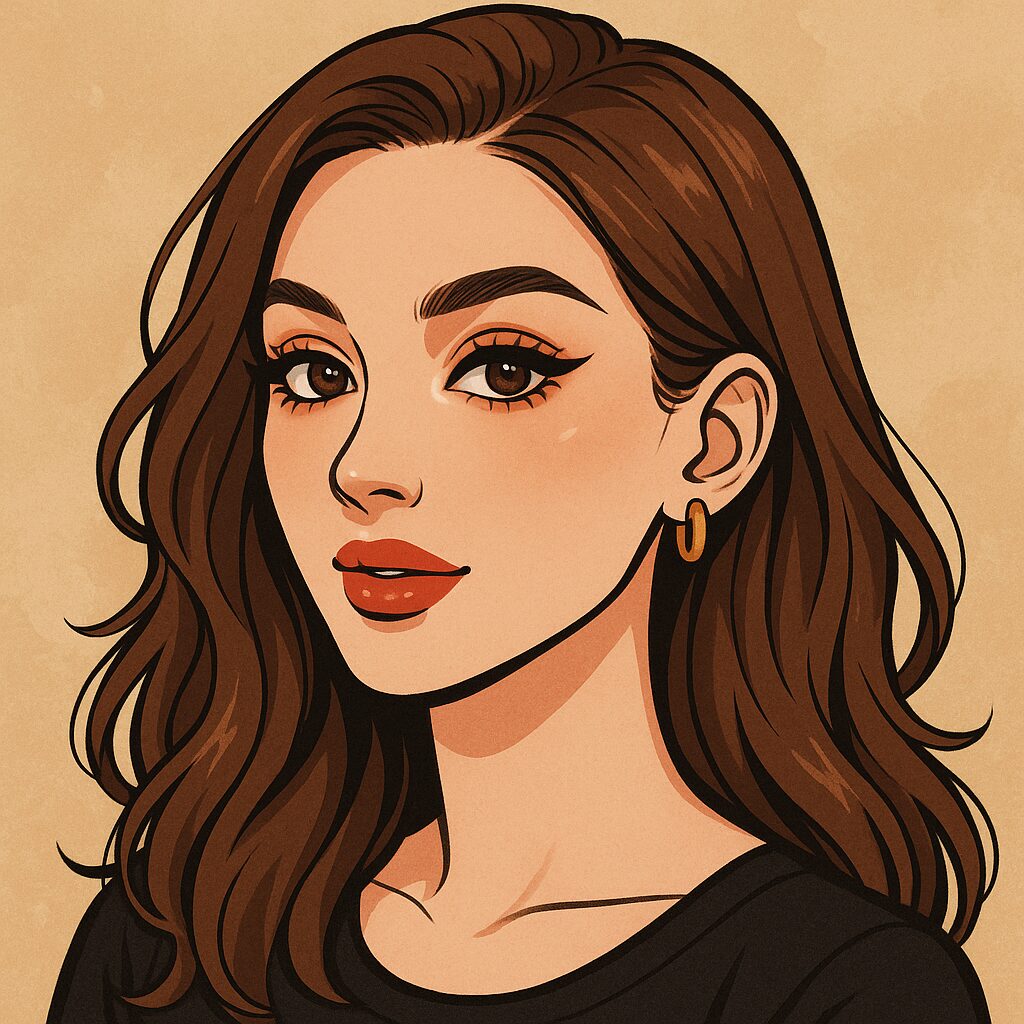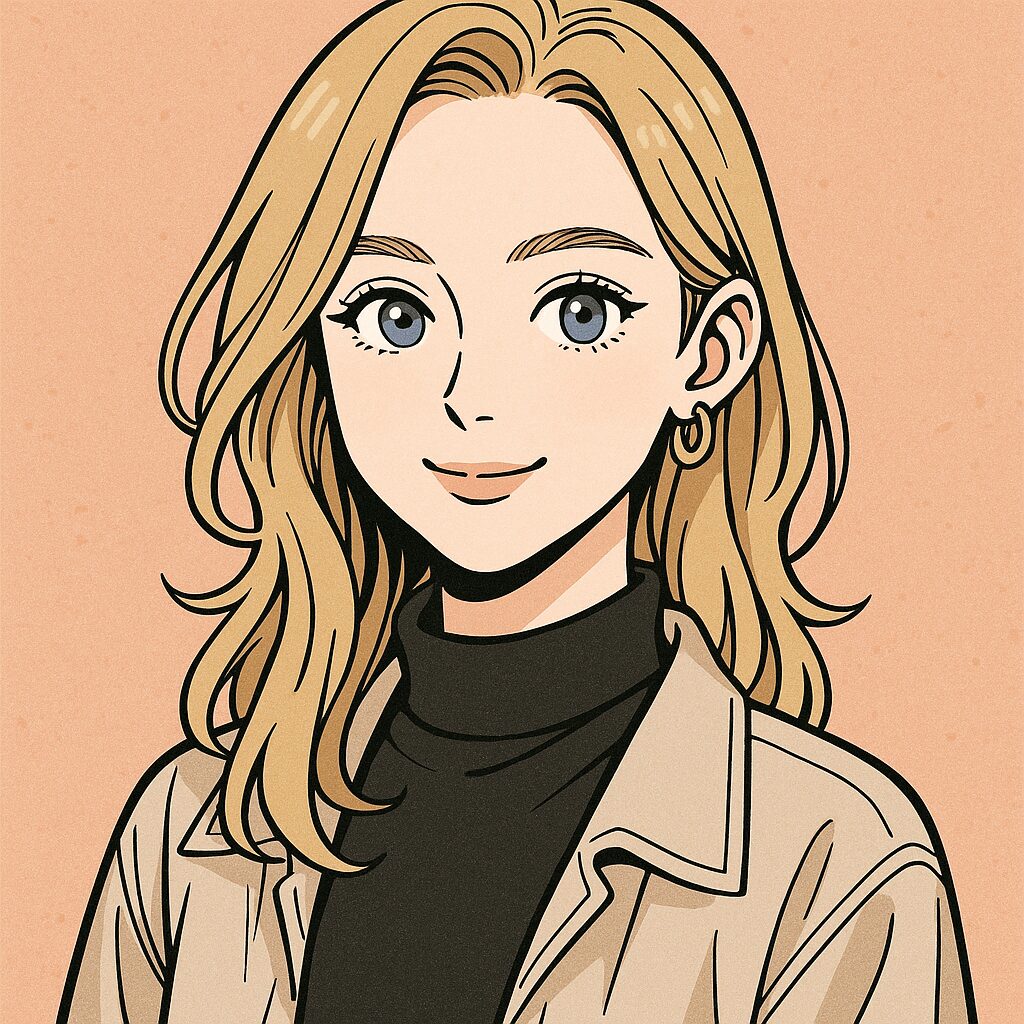昔の日本人と今の日本人を比べたとき、顔立ちが「なんとなく違うな」と感じたことはありませんか?
江戸時代の浮世絵や古い写真を見ると、面長で切れ長の目を持つ人が多く描かれています。一方で現代の街を歩けば、二重まぶたや小顔、鼻筋の通った人も珍しくありません。
こうした違いは「美容整形」や「流行」といった単純な話だけではなく、食生活や生活習慣の変化、西洋文化の流入、美の価値観の変化が大きく影響しています。
この記事では、江戸から現代までの流れを追いながら、日本人の顔立ちがどう変わってきたのかを探ってみましょう。
江戸から明治へ ― 写真に見る“顔立ちの違い”
「日本人の顔立ちが変わったのはいつ?」と聞かれたとき、まず注目したいのが 江戸から明治にかけての大転換期。
ここでは、浮世絵や古写真、そして当時の外国人の記録をヒントに、その変化を見ていきましょう。
江戸時代の“理想の顔”は浮世絵に表れている
江戸時代の浮世絵に描かれる女性は、面長で切れ長の目、すっきりした輪郭が特徴的です。
これは当時の「美の理想像」をデフォルメしたもので、実際の顔立ちが全員そうだったわけではありません。
でも浮世絵が広く流行したことで、こうした顔立ちが「美しい」と感じられていたことがわかります。
-
面長の輪郭=上品で知的な印象
-
細い目=落ち着きと大人っぽさの象徴
-
白粉で白く塗られた肌=清潔感と高貴さのイメージ
今の「かわいい・ぱっちり目」とはかなり違う価値観だったんですね。
明治時代の古写真に残る“リアルな顔立ち”
一方で、明治以降に広まった写真を見てみると、浮世絵とは少し違う印象を受けます。
-
顎や頬骨がしっかりしていて、骨格が大きい
-
顔全体がやや角ばって見える
-
目は一重や奥二重が多く、表情は引き締まっている
これは当時の食事や生活習慣の影響が大きいと考えられます。
硬い食べ物をしっかり噛んでいたため、顎の骨格が現代より発達していたのです。
古写真を並べると、「江戸の理想」→「明治のリアル」 へのギャップが見えてきて、歴史の面白さを感じられます。
外国人が見た“日本人の顔”の印象
当時、日本を訪れた外国人の旅行記や美術本には、こんな記録が残っています。
-
「日本人は背が低く、やせ型で顔が平たい」
-
「目は細く、体格は小柄である」
これは批判ではなく、単なる文化的観察。
彼らにとっては、自国の人々との違いがとても新鮮に映ったのです。
こうした記録からも、当時の日本人の顔立ちが「欧米人とは大きく違っていた」ことがよくわかります。
洋服と洋髪が“顔の印象”を変えた
さらに見逃せないのが、明治から広がった洋装の影響です。
和服は首元や顔の輪郭をすっきり見せる効果がありましたが、洋服や洋髪は逆に「顔の大きさ」を強調します。
そのため、明治期の人々は「顔が大きく見える」という意識を持ち始め、ここから「小顔は美しい」という感覚が芽生えたとも言われています。
ここまでのまとめ
-
江戸時代の理想=浮世絵の面長・細目
-
明治のリアル=写真に残る骨格のしっかりした顔
-
外国人の記録=小柄で平たい顔という印象
-
洋装文化の広まり=小顔志向の始まり
このように、江戸から明治は「理想」から「現実」へと視点が移り、西洋文化の影響も入り始めた時代でした。
.
食生活の変化がつくる顔
日本人の顔立ちを語るうえで、食べ物と咀嚼の習慣は欠かせません。
「何を食べてきたか」が、実は骨格や顔の印象を大きく左右してきたんです。
江戸時代〜明治:米と魚で顎はしっかり
江戸から明治にかけての日本は、米・野菜・魚中心の和食が基本。
干物や根菜など、硬めの食材も多く、咀嚼回数は現代よりずっと多かったといわれます。
-
硬い食材をよく噛む → 顎の骨が発達
-
顔の下半分がしっかりする → 輪郭が大きめに見える
-
米を主食にして魚や大豆を食べる → 筋肉や骨が丈夫になる
この時代の古写真を見ると、顎や頬骨がはっきりしている人が多いのは、この生活習慣の影響だと考えられます。
昭和の学校給食がもたらした変化
時代が進み、昭和になると大きな転換点が訪れます。
それが 学校給食。戦後、パンと牛乳が全国に普及したのです。
-
パン
→ 柔らかく、噛む回数が減る -
牛乳
→ 骨格には良い影響があるが、顎を鍛える要素にはならない -
食事の欧米化
→ 肉料理や加工食品が増え、咀嚼の負担が軽くなる
こうして子どもたちの食生活は一気に変化し、顎が小さくなり始めた時代と言われています。
平成〜令和:柔らかい食事が日常に
現代の日本では、ファストフードやコンビニ食が当たり前になり、柔らかい食べ物を短時間で食べることが増えました。
-
顎が細く、小顔化が進む
-
歯列が狭くなり、歯並びに影響することも
-
「丸顔・小顔」が現代的な特徴として目立つ
一方で「噛む回数を意識しよう」「和食を見直そう」という動きもあり、食と健康をつなげる意識は高まっています。
食生活がつくる“顔の違い”をまとめると
-
昔:
硬い食材をよく噛み → 顎が発達 → 輪郭しっかり -
今:
柔らかい食材が増え → 顎が小さくなる → 小顔・丸顔に
つまり、顔立ちの変化は「遺伝だけではなく、食文化の影響が大きい」ということ。
食生活をたどると、顔立ちの違いがはっきり見えてくるのは面白いですよね。
.
西洋的な“美”の理想が広まった時代
食生活と並んで、日本人の顔立ちに影響を与えたのが 「美の基準」そのものの変化。
特に戦後以降、映画やファッション、雑誌を通じて「西洋的な美しさ」が憧れの対象となりました。
戦後映画がもたらした憧れの顔
戦後の日本に入ってきたハリウッド映画や海外雑誌。
そこで輝いていた女優やモデルたちは、大きな目・高い鼻・立体的な顔立ちを持っていました。
-
日本人にとっては新鮮でまぶしい存在
-
「こんな顔になりたい」という憧れが広まる
-
美容やファッションのトレンドに直結
ここから「西洋的=華やかで美しい」という価値観が定着していきます。
“二重まぶたブーム”の到来
昭和の高度経済成長期、雑誌やテレビでは「二重まぶた」がもてはやされるようになりました。
もともと一重や奥二重が多い日本人にとって、二重まぶたは「華やかさ・明るさ」を象徴するポイントだったのです。
-
アイプチやテープなどのアイテムが登場
-
学生や若い女性の間で大ブームに
-
「ぱっちり二重=かわいい」の図式が完成
この流れは現代のメイク文化にも続いています。
美容整形の一般化
昭和後期になると、美容整形外科が少しずつ広まり始めます。
特に人気だったのは 「二重まぶた手術」。
-
欧米的な顔立ちを目指す人が増加
-
芸能人やモデルが整った顔立ちで注目を浴びる
-
「整えること=恥ずかしいことではない」という意識が徐々に浸透
ただし、この時代はまだ「西洋的に近づく」ことが大きな目的でした。
一方で愛された“和の可愛さ”
でも面白いのは、西洋的な美が流行しても、同時に和の魅力も愛され続けたこと。
昭和のアイドル文化を思い出すと、丸顔であどけない雰囲気の女性たちが国民的スターになっています。
-
一重や奥二重の“素朴な魅力”
-
少し幼さを残した“親しみやすさ”
-
「かわいい=完璧じゃなくてもいい」という価値観
つまり、昭和は「西洋的な華やかさ」と「日本的な可愛らしさ」が共存した時代だったのです。
まとめ:美意識の揺れ動いた時代
-
戦後映画や雑誌
→ 西洋的な顔立ちが憧れに -
二重まぶたブーム
→ 美容アイテムや整形が普及 -
昭和アイドル文化
→ 日本的な“かわいさ”も支持される
このように、昭和〜平成初期は 「欧米的な美しさに近づきたい気持ち」と「日本らしい可愛さを大切にする心」 が入り混じった時代でした。
.
現代日本人の顔立ち ― 多様化と個性の時代
昭和〜平成を経て、令和の今は「ひとつの美の基準」に縛られない時代になりました。
SNSやグローバル化の影響もあり、顔立ちの価値観はかつてないほど多様化しています。
国際結婚・交流で広がる“ミックスの顔”
グローバル化が進み、国際結婚や留学生・移住者との交流が増えたことで、街で見かける顔立ちも多様になりました。
-
ハーフやクォーターといった“ミックス”の人が増加
-
多文化的な見た目が「特別」ではなく「身近」に
-
芸能界やモデル業界でも国際的なルーツを持つ人が人気に
結果として、「日本人らしい顔」「西洋的な顔」といった二分法が意味を持たなくなってきています。
SNSが生んだ“多様な美の基準”
InstagramやTikTokなどSNSの普及によって、世界中の美容トレンドが一瞬で届くようになりました。
-
韓国風の洗練された美人メイク
-
ナチュラルで素朴な和風美人
-
ギャル系・派手系の個性派スタイル
どのスタイルも人気があり、もはや「これが正解」という基準はなくなっています。
むしろ「自分らしい顔立ちをどう活かすか」が重視されるようになったのです。
Z世代の“自己肯定感ある美意識”
若い世代に特徴的なのは、「ありのままの顔を好きになる」流れです。
-
一重まぶたを活かしたメイク動画が人気
-
丸顔を「かわいいチャームポイント」として受け入れる
-
多少のコンプレックスも「個性」としてシェア
これは、過去の「欧米的な顔立ちを目指す」時代とは大きく異なり、よりポジティブで自己表現に近い美意識です。
美容医療は“自然に見えること”が重視される時代へ
もちろん、美容整形やプチ整形も身近なものになりました。
しかし、現代の傾向は「変わるため」ではなく 「自分らしさを活かすため」 に利用する人が増えています。
-
二重整形
→ 不自然にならない、ナチュラル志向 -
ボトックスやヒアルロン酸
→ “やりすぎない”バランスが人気 -
施術後を隠さずオープンに語る人も登場
つまり、美容医療さえも「個性を尊重する時代」に合わせて進化しているのです。
まとめると、現代は“多様性と個性”の時代
-
国際交流の広がり
→ 顔立ちは多様化 -
SNSの普及
→ 美の基準が一気に拡散 -
Z世代
→ 自己肯定感のある新しい美意識 -
美容医療
→ 自分らしさを支える選択肢に
現代日本人の顔立ちは「過去の理想像に近づくこと」ではなく、「自分をどう表現するか」 が大事になってきています。
この流れは今後さらに加速し、未来の日本人の顔立ちは、これまで以上に自由で多彩なものになるでしょう。
.
江戸から令和まで!美人像の変遷
江戸の美人像 ― 浮世絵に描かれた理想
江戸の町を歩けば、色とりどりの着物をまとった女性たち。
当時の美の象徴は、面長で知的な顔立ちに、切れ長の目。浮世絵に描かれる女性たちは、現代の「ぱっちり二重」とはまったく逆方向の美しさを誇っていました。
-
「細い目=上品で落ち着いている」
-
「白粉を塗った白い肌=清らかで高貴」
-
「面長=大人の色気」
こうした美人像は、町人たちの憧れの的。
もし江戸時代にSNSがあったら、きっと「#面長美人」がトレンド入りしていたかもしれませんね。
明治の美人像 ― 和洋折衷のはじまり
文明開化の時代。街角には洋服を着た女性、髪を洋風に結った女性が現れました。
写真館で撮影された明治の女性を見ると、骨格がしっかりしていて存在感のある顔立ちが目を引きます。
そして面白いのは、洋装になることで「顔が大きく見える」という新たな悩みが生まれたこと。
ここから「小顔志向」が芽生えたとも言われています。
さらに、外国人が残した記録には「日本人は小柄で顔が平たい」と書かれていました。
これは批判ではなく、彼らにとって新鮮な驚き。異文化を見た時のリアルな感想だったのです。
昭和の美人像 ― スクリーンとアイドル文化
戦後、日本中を明るくしたのはスクリーンに登場した映画女優たち。
彼女たちの顔立ちは、大きな目・高い鼻・端正な輪郭。まさに西洋的な美への憧れを体現していました。
一方で、高度経済成長とともに「二重まぶたブーム」が到来。アイプチやテープが女子高生の必需品となり、雑誌には「ぱっちり目の作り方」が並びました。
でも同時に、昭和アイドルたちは「丸顔・一重まぶた」の親しみやすさで国民的スターになっていきます。
つまりこの時代は、西洋的美と日本的かわいさが同居したユニークな時代だったのです。
現代の美人像 ― 多様化と個性の時代
令和の今、SNSを開けば「韓国風美人」「ハーフ顔」「ナチュラル和風」など、無数の美のスタイルがあふれています。
どれも正解、どれも個性。
-
Z世代は「一重の自分も好き」と堂々とシェア
-
国際交流で“ミックスの顔立ち”もごく普通に
-
美容医療も「不自然にならない」方向へシフト
つまり現代の美人像は、「自分が自分をどう表現するか」にかかっているんです。
過去の時代にあった「理想の顔一択」ではなく、誰もが主役になれる時代。
.
時代ごとの美人像を彩ったファッションとメイク
美人像は顔立ちだけで決まるものではありません。
その時代に流行した メイクやファッション が重なって、はじめて「美人像」として形づくられていきました。
ここからは、各時代を象徴する“装いの魔法”をのぞいてみましょう。
江戸 ― 白粉と紅がつくる妖艶さ
江戸の美人といえば、まず浮世絵に描かれた女性たち。
彼女たちは、真っ白な白粉で塗られた肌に、真っ赤な紅をさした小さな唇を持っていました。
-
日本髪を高く結い上げることで、顔の面長さが際立つ
-
細い目が“知的で落ち着いた雰囲気”に見える
-
「化粧は身分や格式を映すもの」でもあり、厚く塗られた白粉は裕福さの象徴
もし江戸の町にインスタがあったら、「#白粉美人」「#面長スタイル」が人気タグになっていたかもしれませんね。
明治 ― 和洋折衷の新スタイル
明治になると「文明開化」の風が吹き込みます。
街には和服にブーツを合わせたり、洋傘を差した女性たちの姿がありました。
-
洋髪(カールを入れた髪型)を取り入れる人も登場
-
写真館ではレースやフリルをあしらった洋装が人気
-
和装と洋装が混ざり合う姿は“ハイカラさん”と呼ばれ、憧れの的に
この時代のメイクはまだシンプルですが、「顔を洋装に合わせて小さく見せたい」という意識が芽生え、のちの“小顔志向”の始まりとなりました。
昭和 ― スクリーンがつくった憧れ
戦後の日本を明るくしたのはスクリーンに映る映画スターたち。
女優たちは、アイラインで大きな目を強調し、洋風の口紅で華やかさを演出していました。
-
高度経済成長期
→ 二重まぶたが“かわいい”の象徴に -
雑誌やテレビで「ぱっちり目メイク」のハウツーが大流行
-
70〜80年代のアイドルは逆に“素朴さ”や“ナチュラル感”が売りに
つまり昭和の美人像は、「華やかさと素朴さ」が同居するユニークなスタイルだったのです。
現代 ― 自分らしさを表現するメイクの時代
令和の今、SNSを開けば「美のトレンド」が一瞬で世界から届きます。
-
韓国風メイク:
ツヤ肌+平行眉で洗練された印象 -
ハーフ風メイク:
陰影を強調して立体的な顔立ちに -
ナチュラル和風:
素肌感を活かしてシンプルに
さらにZ世代は「一重メイク研究」や「丸顔アレンジ」など、**自分の顔に合わせた“マイメイク”**をシェア。
美容医療を取り入れる人もいますが、その目的は「変わるため」ではなく「自分らしさを活かすため」になっています。
まとめ
江戸の白粉美人から、明治のハイカラさん、昭和のスクリーンのスター、そしてSNSで自分らしさを表現する令和のメイクへ。
時代ごとに「美人像」を支えたファッションとメイクを振り返ると、美の基準は顔立ちだけでなく“どう演出するか”で変わってきたことがよくわかります。
.
これからの美人像はどうなる?未来の予測
江戸から令和までの美人像を振り返ってきましたが、ここで気になるのは 「これから先の美人像はどう変わるのか?」 ということ。
未来の美人像を考えると、時代の流れとともにいくつかの方向性が見えてきます。
多様性が“前提”になる時代へ
すでに現代は「一重も二重も」「丸顔も面長も」それぞれの魅力が認められる時代。
未来はさらにその傾向が強まり、「みんな違って、みんな美しい」 が本当の意味で根付くでしょう。
-
国際交流や多文化社会の進展
-
“ミックス”の顔立ちが珍しくなくなる
-
「典型的な美人像」という言葉自体がなくなるかも?
デジタルと美の融合
これからは リアルだけでなくバーチャル空間の美 も重要になっていきます。
-
メタバースやAIアバターで「理想の自分」を表現
-
バーチャルインフルエンサーが“新しい美人像”として人気に
-
自分の顔とアバターの間を行き来しながら楽しむ文化が広がる
「オンラインではアバター、オフラインでは自然体」なんてスタイルが当たり前になるかもしれませんね。
健康とナチュラル志向の強まり
未来の美人像を考えると、健康的で自然体な美がもっと評価されるはずです。
-
過度な整形より「表情の豊かさ」や「肌のツヤ」が重視される
-
サステナブルなライフスタイルと美意識が直結
-
「長く生き生きと見えること」が美人像の新しい基準になる
まとめ:未来の美人像は“自由で遊べる”
未来の美人像は「誰かが決める基準」ではなく、ひとりひとりが自由に選び、表現していくものです。
-
ある人はナチュラル派
-
ある人はデジタル空間で理想の顔を楽しむ派
-
ある人は健康美を追求する派
つまり未来の美人像は、「正解がない」ことこそが最大の正解になるのです。
.
まとめ ― 顔立ちの変化は文化の鏡
江戸から令和まで、そして未来へ――。
日本人の美人像は、時代ごとに大きく移り変わってきました。
-
江戸:
浮世絵に描かれた面長で切れ長の目、白粉で彩られた理想の顔 -
明治:
写真に映るリアルな骨格と、洋装がもたらした“小顔志向” -
昭和:
スクリーンのスターに見る西洋的美、アイドル文化に息づく素朴な可愛さ -
現代:
SNSが生んだ多様な美、Z世代の「自分を好きになる」自己肯定感 -
未来:
デジタルと健康志向が重なり、誰もが自由に“自分らしい美”を表現できる時代へ
こうして振り返ると、美人像は単なる顔立ちの変化ではなく、その時代の文化・生活・価値観を映し出す鏡であったことがわかります。
美人像をたどることは、日本の文化の旅をすること。
そしてこれからの未来は、「美の正解がひとつではない」という、最も自由で多彩な時代に向かっていくでしょう。
あわせて読みたい関連記事
この記事では「江戸から令和までの美人像の変遷」をご紹介しました。
でも「顔立ち」や「美の基準」の変化を知ると、もっと深掘りしたくなりませんか?
そんな方におすすめなのがこちらの記事です。
-
👉 [なぜ日本人なのに外国人顔に見える?ハーフ顔の特徴と理由まとめ]
現代の「ハーフ顔人気」の背景を、わかりやすく解説。 -
👉 [昭和の定番メニューと顔立ちの関係?食と文化の変化]
食生活の変化と見た目のつながりに注目したユニークな記事。 -
👉 [登山好きな男性の性格あるある|外見と内面の関係を読み解く記事]
「外見から読み解く性格」シリーズとして、ちょっと視点を変えて楽しめます。
ぜひあわせて読んでみてくださいね。きっと美人像の歴史とリンクして、さらに面白く感じられるはずです。