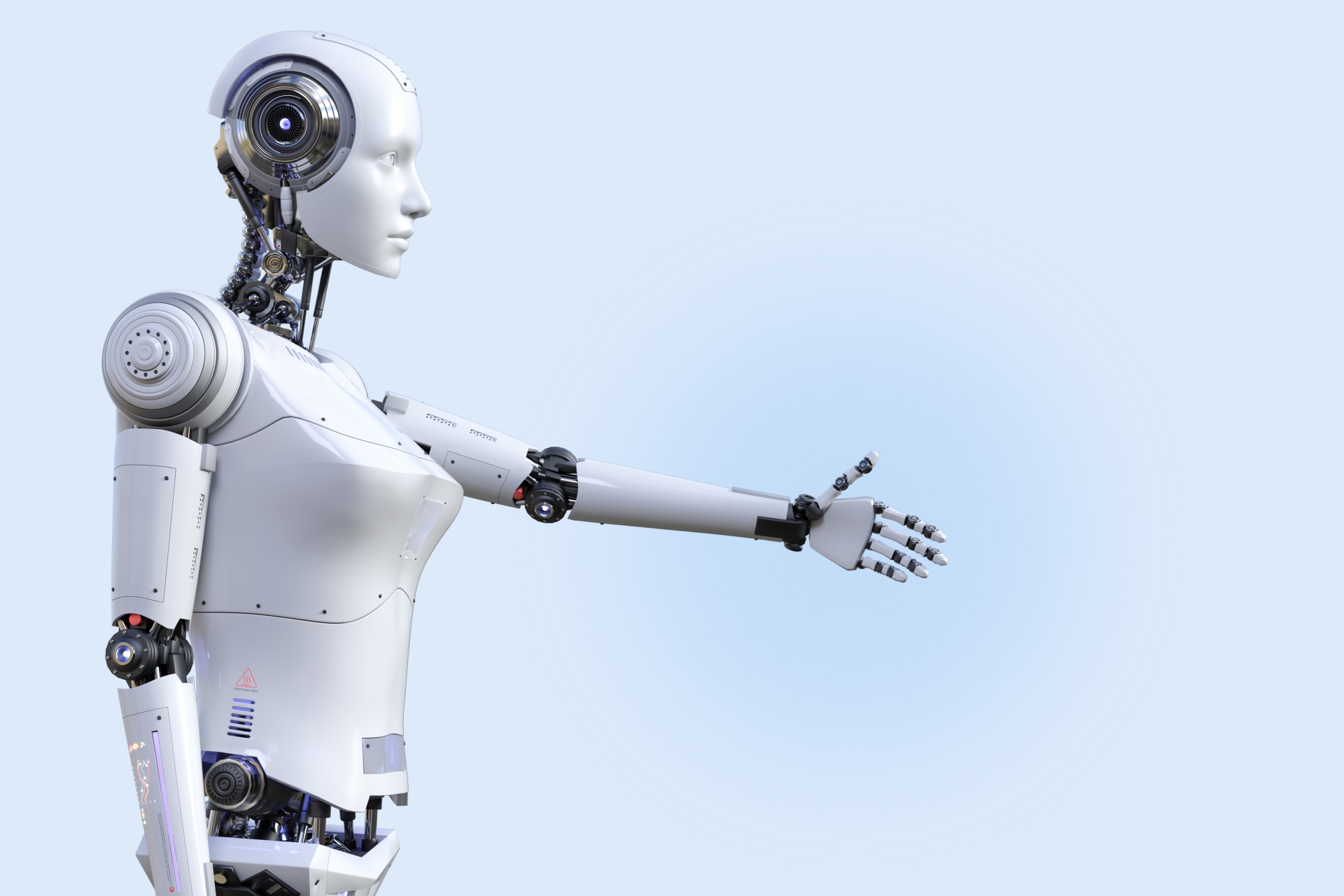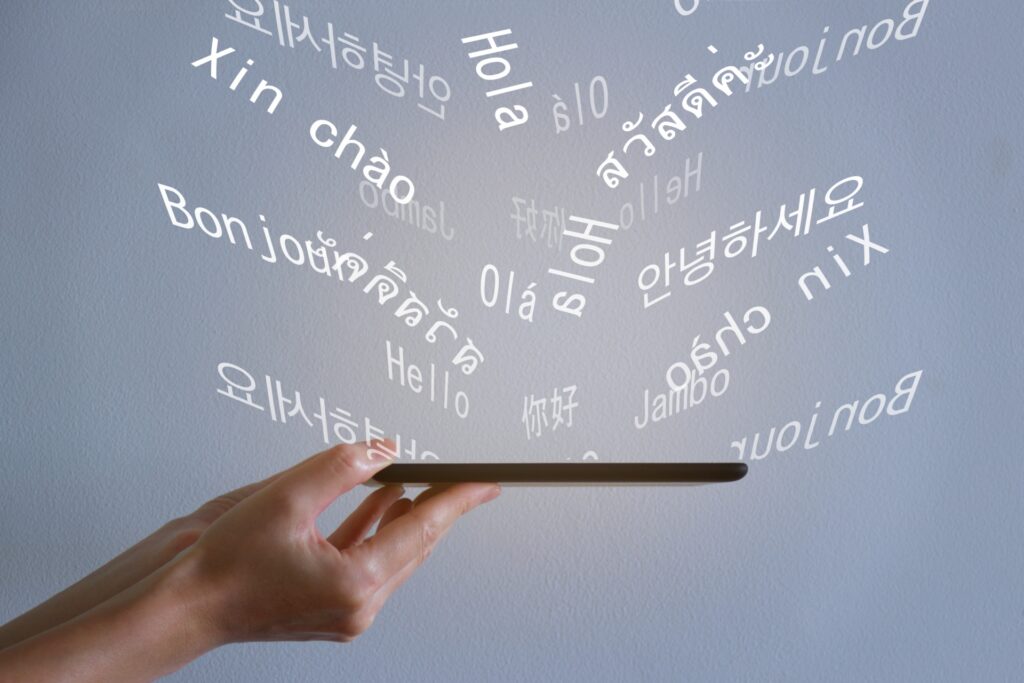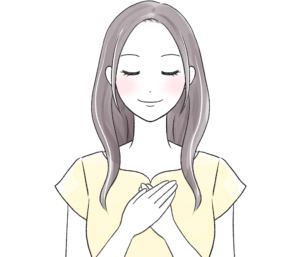「もう一度だけ、会いたい」
そんなふうに願ったことはありますか?
AIの技術が進化した今、亡くなった家族の声や姿を“もう一度”届けてくれる方法が現れました。それは、懐かしい笑顔を再現するものであり、心の奥に残った「伝えたかった想い」と向き合うきっかけになることもあります。
でも一方で、「本当にそれでいいの?」と迷ったり、戸惑ったりする声もあります。このページでは、AIで再現された故人をめぐる“癒し”と“違和感”のあいだにある、さまざまな声を紹介します。
それは、どれが正しいという話ではありません。あなた自身の気持ちと、そっと向き合う時間になりますように──。
AIで再現される“故人”とは?
AI技術の進歩によって、亡くなった大切な人の姿や声を、まるで“もう一度会えた”かのように再現できる時代がやってきました。最近ではテレビ番組やSNSでも取り上げられ、「AI故人」という言葉も耳にするようになっています。
どんな仕組みで再現されるの?
使われるのは、故人の写真や動画、録音された声などの思い出のデータです。それらをAIが学習し、表情の動きや話し方の特徴を再現していきます。こうして、まるで本人が目の前にいるような映像や音声をつくり出すことができます。
どんな想いで使われているの?
たとえば、「お母さんの笑顔をもう一度見たい」「お父さんの“頑張れよ”という声を聞きたい」──そんな家族の切実な想いに寄り添い、AIは映像や声を再現してくれます。悲しみや後悔を抱える中で、“もう一度だけ会いたい”という願いに応える手段として注目されているのです。
どんな場面で使われているの?
このAI技術は、葬儀や法要の場で上映されたり、命日や誕生日などの節目に再生して家族で思い出を振り返る時間に使われています。最近では、自宅で一人で静かに再生する方や、小さなお子さんに“おじいちゃん・おばあちゃんはこんな人だったんだよ”と伝えるために活用するケースも増えてきています。
AI供養は新しい選択肢のひとつ
この技術は、ただの“記録”として残す映像ではなく、「もう一度会えたような気持ちになれる」そんな時間を届けてくれる存在です。まだ新しい供養の形ではありますが、これからの時代に合った“心の寄り添い方”として、少しずつ受け入れられ始めています。
.
賛成の声|AIがもたらす“癒し”と“希望”
グリーフケアの新しい形
大切な人を亡くしたあと、悲しみや寂しさがなかなか癒えないことがあります。このような深い心の痛みをやわらげ、少しずつ日常を取り戻すための心のケアを「グリーフケア」といいます。
AIで再現された故人の姿や声に触れることで、言えなかった「ありがとう」や「ごめんね」の気持ちを伝えるきっかけになったり、懐かしい笑顔に触れて涙があふれたりする人もいます。
「もう一度だけ会いたかった」という気持ちに、少しだけ応えてくれる存在として、AIがグリーフケアの一助になると考える人も増えています。
たとえば、「母の声をAIで聞いた瞬間、胸がいっぱいになった」「亡くなった祖父が『大丈夫だよ』と言ってくれた気がして、心が救われた」など、感動の声も聞かれます。
家族の思い出を共有できる
特に小さな子どもや孫にとって、会ったことのない祖父母の姿や声を知るきっかけになるという意義も。写真だけでは伝わりにくい人柄や空気感を、AIはやさしく教えてくれる存在になりつつあります。
「ありがとう」が聞けるだけで救われる
「もう一度だけ、声が聞きたい」そんな願いを叶えるAI技術。亡くなった家族が「大丈夫だよ」「がんばって」と語りかけてくれることで、心の支えになる人も多いようです。
.
反対の声|迷いや不安の声にも耳を傾けて
AIで故人を再現することには、やさしい気持ちだけでは語れない“気になる点”もあります。ここでは、よく聞かれる3つの不安について、わかりやすく紹介していきます。
故人が望んでいない可能性がある
AIで再現される場合、多くは家族や周囲の人の判断で進められます。でも、亡くなった方が「自分をAIで再現してほしい」と思っていたかはわかりません。
生前に「そういうのはちょっと…」と話していた方もいるかもしれません。たとえ家族の愛情からの行動でも、本人の気持ちを想像すると、少し立ち止まりたくなることもあります。
気持ちが整理しづらくなることも
AIによって“また会えたような気持ち”になれる反面、いつまでもお別れができず、心の整理が難しくなってしまうこともあります。
とくに、突然のお別れだった場合、「もういない」という現実を受け入れるのに時間がかかることもあります。「毎日AI動画を見てしまう」「何度も話しかけてしまう」といった声もあり、悲しみが深いほど、依存してしまうリスクもあるのです。
宗教や文化による違和感
宗教の考え方によっては、「亡くなった人は天に旅立った存在」とされていることも多くあります。たとえば仏教では「成仏」、キリスト教では「天に召される」と表現されます。
そうした考えの中では、「再びこの世に呼び戻す」ことに違和感を覚える方もいます。「あれは本人ではない」「魂はそこにいない」という考え方もあり、AIの再現に抵抗を感じるのも自然なことです。
このように、AI故人はとても便利で感動的な技術ですが、誰にとっても“やさしいもの”とは限りません。それぞれの価値観や信じていること、大切にしている想いをふまえて、慎重に向き合うことが大切です。
SNSでも話題に|実際に再現された事例とリアルな反応
50代女性・母を亡くして1年後の体験
「最初は正直、AIなんてちょっと怖い…という気持ちがありました。でも、SNSで『お母さんが笑って話すAI動画』を見かけた時、なぜか心が動いて。
自分も、もう一度だけ会いたいと思ってお願いしました。動画で『がんばってね』と母の声を聞いたとき、涙があふれて止まりませんでした。本物ではないけれど、今の自分に寄り添ってくれる“存在”に救われた気がしました」
40代男性・父の声をAIで再現して感じたこと
「父とは最後までうまく話せずに終わってしまって…。だから、AIで再現できると聞いて『もう一度、ちゃんと向き合いたい』と思ったんです。
でも実際に再現された父の声を聞いたとき、うれしさよりも“なんだか違う”という気持ちが残りました。父のことを思い出すきっかけにはなったけれど、やっぱり“声”だけでは気持ちは埋まらないのかもしれません」
SNSでの声もさまざま
ある女性が母の写真からAI動画を作成したという事例が話題になりました。「母が笑って話しかけてくれる姿に涙が止まらなかった」と語る彼女。一方でネット上には「そこまでして会いたいの?」「ちょっと怖い」といった声もあり、反応は分かれています。
- 「父の声をもう一度聞きたい、私ならお願いするかも」
- 「技術はすごいけど、心が追いつかない気がする」
- 「本人の意思が確認できないなら、使うのは慎重にしたい」
あなたはどう思う?意見が分かれる時代の供養スタイル
AIで故人と再会できることに反応はわかれています。ここでは、さまざまな立場からの受け止め方を整理してみました。
癒しになる人もいれば、戸惑う人も
今は“正解のない時代”。AIで再現された故人との対話が、癒しになる人もいれば、不安やモヤモヤにつながる人もいます。亡き人の声を聞いて「生きる力をもらえた」と感じる人もいれば、逆に「かえって悲しみが深まった」と感じることも。
共通しているのは“誰かを想う気持ち”
ただ、共通しているのは「大切な人と、もっと話したかった」「もっと一緒にいたかった」という切実な想いです。AIを使うかどうかに関係なく、その気持ちはとても自然で、やさしいものです。
大切なのは、自分の気持ちに正直でいること
他の人がどう思うかよりも、自分自身が「どんな形で供養したいのか」「どうしたら心が落ち着くのか」に耳を傾けることが大切です。AI供養を選ぶ人も、昔ながらの方法を大切にする人も、自分にとって“ちょうどいい供養”を見つけられたら、それがきっと一番の答えになるのだと思います。
現代ならではの供養のスタイルに迷っている方は、こちらの記事もご覧ください。
→ 家族でのお墓参りが正直しんどいと思う私はダメなのか。。
今、できる“優しいお別れ”の選び方
AI技術による新しい供養が話題になる一方で、「やっぱり昔ながらの方法が落ち着く」という方も多いのではないでしょうか。ここでは、テクノロジーを使わずにできる“やさしいお別れの仕方”をご紹介します。
たとえAIを使わなくても、大切な人を思い出し、心を込めて過ごす時間には、変わらぬあたたかさがあります。
手紙に気持ちを込めてみる
言えなかった「ありがとう」や「ごめんね」を、手紙にして綴ってみることも立派な供養の一つです。声に出すのが難しくても、紙に書くことで心が整理され、気持ちが少しずつ軽くなることもあります。
思い出の写真や動画を見返す
昔のアルバムや動画を見ながら、家族や友人と故人の思い出を語る時間は、心をあたためてくれます。「あの時こうだったね」と笑い合うことも、やさしいお別れの一歩になるかもしれません。
静かな場所で心を整える
お墓参りだけでなく、自然の中や自分だけの“静かな場所”で、そっと故人のことを思い出す時間も大切です。大切な人に語りかけるように、自分の心と向き合うことで、穏やかな気持ちになれることがあります。
AIに頼らずとも、手紙を書いたり、思い出を話したり、お墓参りをしたり──昔ながらの方法にも、心を癒す力があります。
技術の力はすばらしい。でも、立ち止まって自分の心に問いかける時間も、同じくらい大切なのかもしれません。
「お墓に行けない時の心の寄せ方」については、こちらの記事も参考にどうぞ。
→ お墓参りに行けない時の代わりにできること7選
.
変わっていく供養の形、変わらない“想い”
昔ながらの供養に込められた“手を合わせる想い”
かつては、供養といえばお墓参りやお仏壇に手を合わせることが一般的でした。写真や遺影を見ながら、静かに心の中で語りかける──そんな“アナログな供養”に、私たちは自然と慣れ親しんできました。その時間は、亡き人への感謝や祈りを込めた、静かな対話でもありました。
デジタルで広がる“新しい祈り方”
AIやテクノロジーの進化によって、供養のスタイルも多様化しています。仮想空間に建てたお墓、スマホで手軽にできる供養アプリ、そしてAIで再現された故人の姿や声──。
こうした“新しい祈りの形”は、時間や距離を越えて、誰かを思う気持ちをより身近に、日常的に届けてくれる手段となりつつあります。
スマホひとつでできる供養や、手元供養アプリなどについては、こちらの記事も参考にどうぞ。
→ スマホ供養って何?今どきの供養スタイルと心の整え方
変わらないのは“人を思う心”
たとえ供養の方法が変わっても、そこに込められた気持ちは昔と変わりません。「もう一度会いたい」「想いを伝えたい」「忘れたくない」──そう願う心は、どの時代にも共通する人間らしい感情です。
供養とは、形式ではなく“想い”に寄り添う時間。その本質を大切にすれば、どんな方法を選んでも、それはきっと、やさしい供養になるのではないでしょうか。
.
私だったら、どう感じるだろう?
もし、私の父がAIで再現されたら──正直に言うと、すぐに「うれしい!」とは言いきれないかもしれません。画面の中で笑っている母を見て、きっと最初は戸惑ってしまうと思います。「これは父なの? それとも父に似た何か?」と、気持ちが揺れるかもしれません。
でも、それでもやっぱり会いたい。声を聞きたい。たとえ本物じゃなくても、「がんばってるね」と一言かけてもらえたら、それだけで心が軽くなる日もある気がするのです。
AIの力で“もう一度”を叶えられる時代。だからこそ、ひとりひとりの「その時の気持ち」を大切にしたいなと思います。無理に使わなくてもいいし、使って涙してもいい。誰かを思う心に、間違いなんてないと思うのです。
あわせて読みたい関連記事
.
まとめ
AIで再現された故人との“再会”──それは希望にもなれば、戸惑いにもなり得ます。大切なのは、誰かの決めた正しさではなく、自分の心に正直であること。供養の形も、愛し方も、ひとつじゃなくていい。だからこそ、あなたの感じたその気持ちを、大事にしてくださいね。