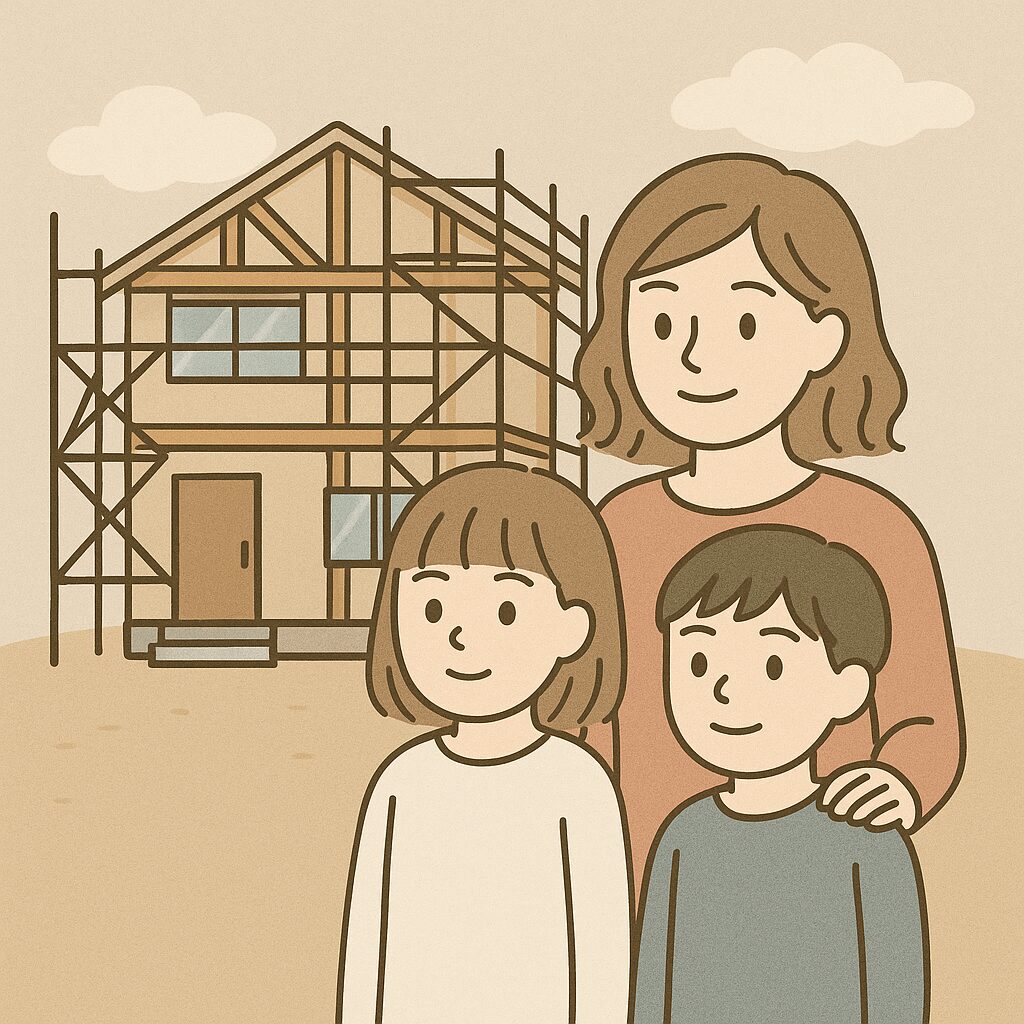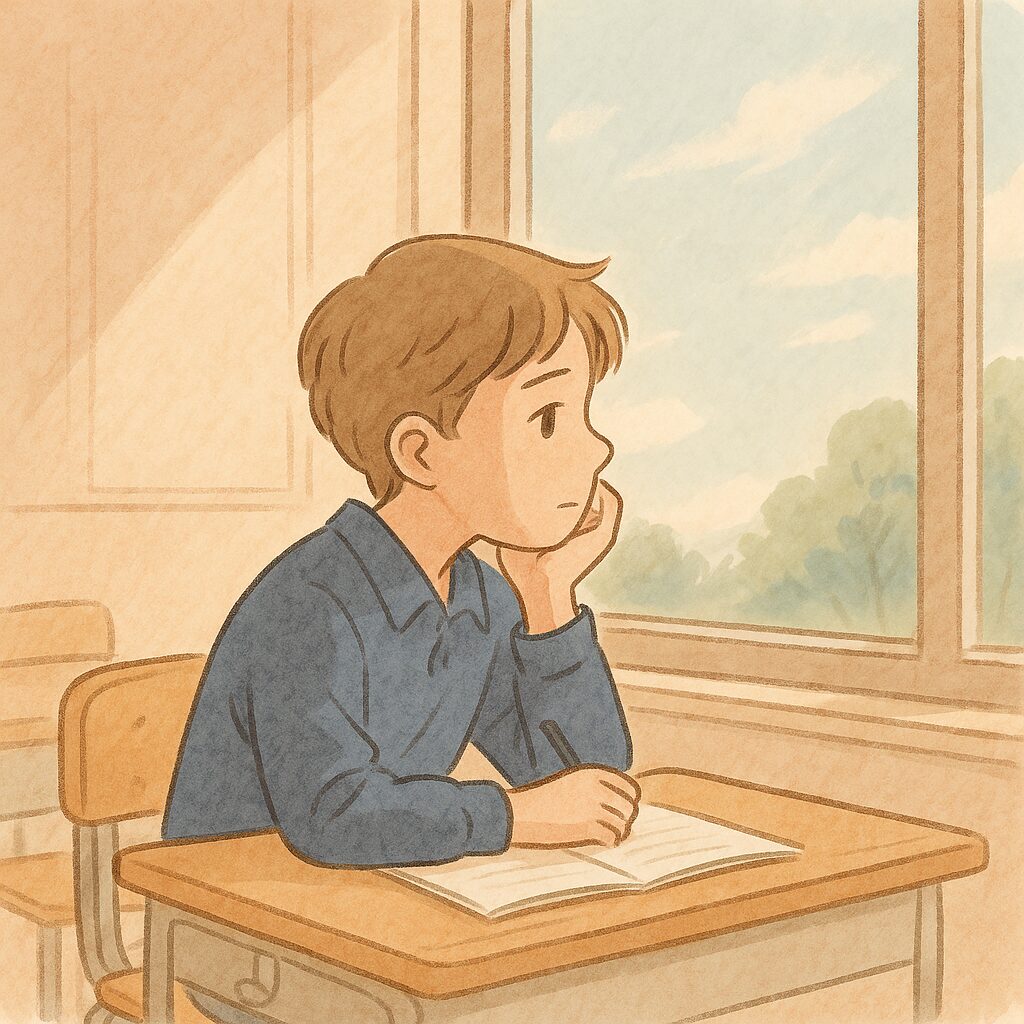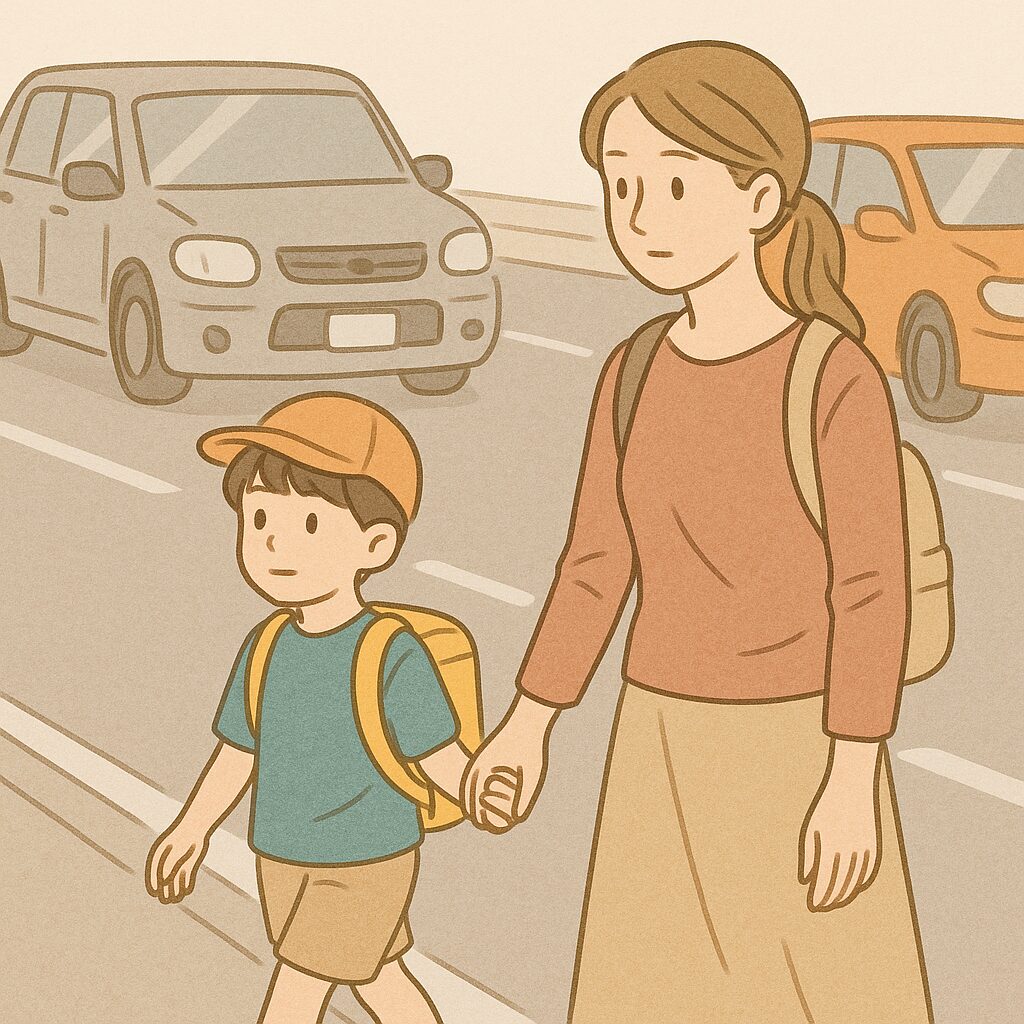小学校や中学校の入学・進級の時期になると、「学区外通学ってできるの?」と悩む方も多いですよね。
たとえば、共働きで送迎が難しいご家庭や、転居予定・安全面の不安があるケースなど、
それぞれの事情に合わせて通学先を検討するご家庭が増えています。
この記事では、教育委員会に提出する「学区外通学理由書」の書き方を、
具体的なパターン別の例文つきでくわしく紹介します。
共働き・転居・安全面・兄弟同校・人間関係など、よくある申請理由をすべてカバーしていますので、自分のケースに近い部分を参考にしてみてくださいね。
また、最後には提出時の注意点や、自治体による違いにもふれています。
「どう書けば伝わるか」を迷っている方に、少しでも安心のヒントになりますように。
① 共働き・送迎の都合による場合(例文3パターン)
共働き家庭では、登下校の見守りや送迎の時間が確保できず、安全面や生活リズムの面で学区外通学を希望するケースが多く見られます。
教育委員会でも「保護者の就労状況」はよく考慮されるポイントです。
ここでは、実際の家庭のパターンに合わせた3つの例文を紹介します。
🕓 パターン①:勤務時間が合わず登下校の見守りが難しい場合(小学校向け)
私たちは共働き家庭であり、登下校の時間帯に保護者が不在となることが多くあります。
勤務時間の都合上、指定校よりも〇〇小学校のほうが通学経路が安全で、
祖父母宅からも見守りがしやすい環境です。
子どもの安全を第一に考え、学区外通学を希望いたします。
✅ポイント
-
「時間帯に不在」「見守りが難しい」など家庭の現実を明確に
-
「安全」と「見守り体制」の両立を伝えると通りやすい
❌NG例
共働きなので、近くの学校のほうが都合がいいです。
→ 「都合がいい」は保護者の希望として扱われやすい。
「子どもの安全を第一に」と表現するのがコツ。
🚗 パターン②:早朝・夜間勤務がある場合(小中共通)
保護者の勤務が早朝および夜間にかかることがあり、登下校の送迎や見守りが難しい状況です。
〇〇小学校(中学校)は通学路が明るく交通量も少ないため、
安全面を考慮して学区外通学を申請いたします。
子どもが安心して登下校できるよう、どうぞご配慮をお願いいたします。
✅ポイント
-
「勤務時間の実情」+「安全な通学経路」をセットで説明
-
シフト勤務など、日によって見守りが難しい場合にも応用できる
❌NG例
夜遅くまで働いているので、送り迎えができません。
→ “できません”よりも“難しい状況です”の方が柔らかく誠実な印象。
🌃 パターン③:部活動や帰宅時間が遅くなる中学生の場合(中学校向け)
私たちは共働き家庭であり、子どもの部活動終了後の帰宅時間が遅くなることがあります。指定校までの通学路は人通りが少なく、夜間照明も少ないため、安全面に不安があります。
通学経路が明るく、駅からの距離も短い〇〇中学校を希望いたします。
子どもの生活リズムと安全を考慮し、学区外通学を申請いたします。
✅ポイント
-
「夜間帰宅」「照明が少ない」など現実的な理由を具体的に
-
“生活リズム+安全面”のセットは教育委員会でも評価されやすい
❌NG例
部活があるから、家の近くの中学校に行かせたいです。
→ “行かせたい”では主観的。
“安全に通学できるように”と書き換えることで公的文書らしくなります。
🌿 まとめ:共働き理由で通すコツ
-
「勤務時間」や「見守り困難な時間帯」を具体的に書く
-
「子どもの安全」「家庭の支援体制」を中心に据える
-
「共働き=親の都合」ではなく「安心して登校できる環境の確保」と伝える
💡補足
勤務証明書や勤務先住所を添付すると、申請の信頼性が高まります。
可能であれば「勤務時間(シフト)を示す表」も併せて提出するとよりスムーズです。
.
② 祖父母宅から通う場合(生活の拠点が2か所)
共働きや単身赴任などの事情で、平日は祖父母宅から通う子どもも多くなっています。
「生活の中心が祖父母宅にある」と判断されると、認められやすいケースです。
【小学校】祖父母宅から通う場合の例文
平日は祖父母の家で過ごしており、登下校の見守りも祖父母にお願いしています。
祖父母宅近くの〇〇小学校が生活リズムに最も適しているため、
学区外通学を希望いたします。ご理解いただけますと幸いです。
✅ポイント
-
“平日滞在”など、実際の生活パターンを具体的に書く
-
「祖父母が登下校を見守る」など安全面も添える
❌NG例
祖父母の家が近いので、そちらの学校に行かせたいです。
→ “近い”だけでは生活拠点と見なされません。
“日常的に祖父母宅から通っている”実態を明示することが重要。
【中学校】祖父母宅から通う場合の例文
平日は祖父母の家で過ごすことが多く、部活動の帰宅時間も祖父母が見守っています。
通学経路や夜間の安全を考慮し、祖父母宅近くの〇〇中学校への通学を希望いたします。
✅ポイント
-
中学生ならではの「部活・夜間帰宅」要素を入れると◎
-
「祖父母の見守り」と「夜間安全」をセットで書く
❌NG例
祖父母が送迎してくれるので別の中学校にしたいです。
→ “送迎してくれる”だけでは家庭の必要性が伝わらない。
“安全な通学ルート”や“家庭の生活リズム”と絡めると通りやすくなります。
.
③ 転居予定・新居建築中の場合
「近々引っ越しを予定している」「新居ができるまで仮住まい」など、
転居を理由に学区外通学を希望する家庭も少なくありません。
教育委員会では、“転居が確定している”か、“計画段階なのか”によって判断が分かれるため、
できるだけ具体的な時期・住所・背景を書くことがポイントです。
🏡 パターン①:転居が確定している場合(契約・購入済み)
私たちは〇月に〇〇市〇丁目への転居が決まっており、現在新居の入居準備を進めております。
新生活の開始にあわせて、子どもが早い段階で通学環境に慣れられるよう、
転居先の学区にある〇〇小学校への学区外通学を希望いたします。
生活リズムを安定させ、学年途中の転校による不安を避けたいと考えております。
どうぞご理解のほどお願いいたします。
✅ポイント
-
「〇月に転居予定」「住所(町名まで)」など具体性を出す
-
「生活リズム」「心理的負担」など子ども中心の表現を入れると好印象
-
契約書や入居予定通知など、証明書類を添付するとよりスムーズ
教育委員会は「転居が確定している」場合、学期途中の転校を避けるために柔軟に対応してくれることが多いです。
転居の事実を示す書類を添えると、審査担当者も安心して判断できます。
🚚 パターン②:転居が未確定だが計画中の場合(柔らかい表現)
現在、〇〇地区への転居を検討しており、通学先の〇〇中学校周辺で住宅を探しています。
今後の生活拠点を見据え、子どもが早い段階で地域に馴染めるよう、
学区外通学を希望いたします。転居が決まり次第、速やかに住所変更手続きを行う予定です。
✅ポイント
-
「検討中」「住宅を探している」など現実的な表現でOK
-
“地域に馴染めるように”など教育的・心理的配慮を入れると好印象
💬補足メモ
「いつか」「いずれ」は避け、“時期未定だが準備中”とする
「検討中」でも、誠実に目的を書けば問題ありません
行政担当者は“誠実さ”を見ているため、曖昧な表現でも正直であれば通るケースあり
🏘️ パターン③:仮住まい・二重生活中の場合(補足例文)
現在、新居の建築中につき、一時的に仮住まい(〇〇市〇丁目)からの通学となっております。
新居完成後も同じ学校へ通えるよう、転居先学区の〇〇小学校への学区外通学を希望いたします。
短期間での転校による子どもの負担を考慮し、継続して安心できる環境を確保したいと考えております。
✅ポイント
-
「仮住まい」「二重生活」などは家庭の事情として認められやすい
-
「転校負担」「継続性」「心理的安定」を明確に書く
❌NG例
新しい家が建つまで仮の家なので、同じ学校に行かせたいです。
→ “行かせたい”よりも“通えるよう希望いたします”で公文書らしく整える。
🌿 まとめ:転居理由を伝えるときのコツ
-
「いつ」「どこに」引っ越すのかをできるだけ具体的に
-
子どもの“通学環境の安定”を中心に据えて説明
-
証明書類(契約書・工事日程・住宅探し中の資料など)があれば添付
💡転居理由は「生活の変化」ではなく「安定のための準備」として書くと、行政側も理解を示しやすくなります。
.
④ 人間関係・心身の不調による場合(いじめ・不登校を含む)
子どもが学校生活で心に傷を負ったり、人間関係に悩んで不安定になるケースは、どの家庭にも起こりうることです。
「いじめ」「孤立」「人間関係の摩擦」など、直接的な表現は避けつつも、
保護者として子どもの安全と安心を守る姿勢をしっかりと伝えることが大切です。
教育委員会も、子どもの心身の健康に関わる事情については、
学区外通学の理由として柔軟に受け止めてくれることが多いです。
🌿パターン①:心身の不調・環境を変えたい場合(やさしい表現)
子どもが現在の学校環境において、登校に強い不安を感じる日が増えております。
医師からも「環境を変えることで安定が見込まれる」との助言を受けており、
少しでも安心できる環境で学ばせたいと考えております。
子どもの心身の安定を最優先に、〇〇小学校(中学校)への学区外通学を希望いたします。
どうかご理解のほどよろしくお願いいたします。
✅ポイント
-
「いじめ」や「トラブル」などは避けつつ、状況を具体的に
-
「登校に不安」「心身の安定」など中立的な言葉を使う
-
第三者(医師・カウンセラー)の助言があると安心感が高まる
💬パターン②:人間関係によるストレスや登校拒否傾向がある場合
学校での人間関係により、登校への不安を強く感じております。
学校とも何度か相談を重ねておりますが、環境を変えることで
子どもが前向きな気持ちを取り戻せると考えています。
安全で穏やかな環境で学び直せるよう、〇〇中学校への学区外通学を希望いたします。
どうか子どもの心の回復を第一にご配慮いただけますようお願いいたします。
✅ポイント
-
「いじめ」と断定せず、「人間関係」「登校への不安」で表現
-
「学校と相談を重ねている」と入れることで誠実な印象
-
“回復”“前向きな気持ち”などポジティブな表現を加えると柔らかい
🕊パターン③:心療内科・カウンセリングの助言がある場合(医療的根拠を添える形)
現在、子どもは学校生活での不安や緊張が続いており、心療内科での診察を受けております。
医師からも「環境を変えることで症状の改善が見込まれる」との指導をいただいております。
子どもの心身の安定と継続的な学習環境の確保のため、〇〇小学校(中学校)への学区外通学を希望いたします。
どうか温かいご理解をお願いいたします。
✅ポイント
-
医師・心理士・スクールカウンセラーなど“専門家の助言”を示す
-
診断名を書く必要はなく、「助言を受けた」だけで十分
-
「改善」「安定」「継続的な学習環境」などの言葉が信頼されやすい
🌷書き方のコツ
-
「登校が難しい」「学校環境への不安」「心身の不調」など中立的表現を使う
-
「いじめ」という言葉は極力避け、具体的な状況と改善への意志を伝える
-
行政は「家庭の努力・相談姿勢」を重視するため、「学校とも相談」や「医師の助言」などが入ると好印象
🌿補足
本記事で紹介している例文は、あくまで一般的な記載例です。
学区外通学の可否や手続き内容は自治体によって異なりますので、
実際に申請を行う際は、教育委員会やスクールカウンセラーなど専門機関へご相談ください。
💖あとがき
子どもの気持ちは、言葉にできないほど繊細なもの。
だからこそ、「環境を変える」という選択も、決して逃げではなく、“もう一度笑って登校できるように”という親の願いなんですよね。
私も長女の時に、親として同じ体験をしました。だからこそ、同じように悩んでいる方の参考になれば幸いです。
⑤ 兄姉が同じ学校に通っている場合
兄弟姉妹がすでに別の学校に通っている場合、
登下校や学校行事をそろえることで家庭の負担を軽減できるという実際的な理由があります。
特に共働きや送迎を伴う家庭では、「一緒の学校で見守れること」が大きな安心材料になります。
【小学校】兄姉が通っている場合の例文
現在、姉(兄)が〇〇小学校に在学しており、
登下校を一緒に行うことで安全面でも安心できると考えております。
行事や学校生活を兄妹で共有できることも大切にしたいと考え、
同じ学校への通学を希望いたします。ご配慮のほど、よろしくお願いいたします。
✅ポイント
-
“安全面+家庭の生活リズム”を中心に書く
-
“兄妹で一緒に登下校できる”という表現が効果的
❌NG例
上の子と同じ学校に行かせたいです。
→ 希望の気持ちだけでは伝わらないので、
“家庭の負担軽減”や“登下校の安全”を理由に変換しましょう。
【中学校】兄姉が通っている場合の例文
現在、姉(兄)が〇〇中学校に在学しており、
同じ学校で学ぶことで、通学・部活動・学校行事などにおいて家庭のサポートがしやすくなります。
通学経路の安全性も確認しており、学区外通学を希望いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
✅ポイント
-
中学生の場合は“部活動・行事・帰宅時間”も含めると◎
-
“家庭でのサポートがしやすい”という具体性を出す
❌NG例
上の子が通っているので、下の子も同じ学校にしたいです。
→ “なんとなく一緒がいい”印象になってしまうため、
“学校生活を家族で支えやすい”“通学経路の一貫性”など、現実的な理由に変えるのがポイント。
🌿 ワンポイントアドバイス
「兄姉が通っている」は感情面よりも“効率と安全”の視点で書くのがベターです。
特に中学校では、帰宅時間や部活動の終了時刻が重なるなどの要素を入れると、より説得力が増します。
.
⑥ 医療・発達支援など特別な事情がある場合
通院や支援センターへの通所など、健康や発達面での配慮が必要な場合、
学区外通学は比較的許可されやすい理由です。
教育委員会では「学びの継続」と「健康維持の両立」を重視しており、
医師の意見書や支援計画書を添えることで、より理解されやすくなります。
【小学校】通院・支援が必要な場合の例文
定期的に〇〇クリニックへの通院があり、
通院と学習を両立させるためには〇〇小学校が最も通いやすい距離にあります。
子どもの健康面と生活リズムを考慮し、学区外通学を希望いたします。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
✅ポイント
-
「通院の頻度」「場所」「通いやすさ」を具体的に
-
“健康と学習の両立”をキーワードに書くと誠実な印象
❌NG例
通院しているので、通いやすい学校に変えたいです。
→ “通いやすい”だけでは弱い。
“具体的な通院先名”や“通学との両立”をセットで書くとよいです。
【中学校】通院・発達支援がある場合の例文
〇〇医療センターへの定期通院、および週1回の発達支援センター利用があり、
学校と医療機関が近い〇〇中学校を希望いたします。
学業と療育の両立を無理なく続けるため、学区外通学を申請いたします。
どうぞご理解のほどお願いいたします。
✅ポイント
-
中学生の場合は「通院+支援機関+スケジュール負担」を入れる
-
「学業・療育の両立」という表現は行政文書でも評価されやすい
❌NG例
通院のために近い中学校のほうが助かります。
→ “助かります”という感情語よりも、“両立のために必要”という客観的表現に置き換えると効果的。
🩺 添付書類・説明のコツ
医療・支援関係の申請では、以下のような書類を添えるとスムーズに審査が進みます。
-
診断書または通院証明書
-
支援センター・放課後デイサービスの利用証明
-
通院経路の地図(通学ルートと合わせて示すと◎)
また、「家庭内での見守り体制」や「通院の付き添い状況」も一文加えると、
生活の実情が伝わりやすくなります。
.
⑦通学距離・安全面による場合
子どもの通学は「毎日のこと」だからこそ、安全面を理由にした学区外通学の申請はとても多いです。
教育委員会も「登下校の安全確保」は最も重視する項目のひとつ。
特に、交通量・距離・坂道・夜道など、客観的な危険要素を具体的に説明することで、
誠実かつ説得力のある理由書になります。
🚸 パターン①:交通量が多く横断が危険な場合(小学校)
自宅から指定校までの通学路には、交通量の多い幹線道路を横断する箇所があり、
登下校の際に車の往来が多く、信号も少ないため安全面で不安があります。
徒歩で安全に通える〇〇小学校のほうが安心して登校できると判断し、
学区外通学を希望いたします。ご理解のほどお願いいたします。
✅ポイント
-
「信号が少ない」「交通量が多い」など具体的な危険要素を記す
-
「徒歩で安全に通える」など、対策をセットで伝えると効果的
❌NG例
車が多くて危ないから、近くの学校にしたいです。
→ “危ない”だけでは主観的。
“交通量が多く信号が少ないため”など事実ベースの説明に。
⛰ パターン②:坂道や距離が長く、悪天候時に危険な場合(小学校)
自宅から指定校までは片道約25分の通学距離があり、途中に急な坂道が複数あります。
雨天や積雪時には滑りやすく転倒の危険もあるため、安全面を考慮して、
通学距離が短く見通しのよい〇〇小学校への学区外通学を希望いたします。
ご配慮のほどよろしくお願いいたします。
✅ポイント
-
距離や所要時間を数字で示すと信頼度アップ(例:片道25分など)
-
地形や天候によるリスクを具体的に入れる
❌NG例
坂が多いので、別の学校に行かせたいです。
→ “坂が多い”だけでは弱い。
“滑りやすく転倒の危険がある”“冬季は除雪が遅い”などを補足すると◎。
🌃 パターン③:夜間帰宅時の安全を考慮する場合(中学校)
子どもが部活動を終えて帰宅する時間が遅く、
指定校までの通学路は街灯が少なく人通りも少ないため、安全面に不安があります。
駅から明るい道で帰宅できる〇〇中学校のほうが、夜間でも安心して通えると判断し、
学区外通学を申請いたします。どうぞご理解をお願いいたします。
✅ポイント
-
“夜間照明の少なさ”や“人通りの少なさ”は行政的に理解されやすい
-
「部活動」「帰宅時間」など中学生ならではの生活リズムを入れる
❌NG例
帰り道が暗いので、別の中学校にしたいです。
→ “暗い”だけでは弱い。
“街灯が少なく人通りが少ない”など、安全確保のための判断と書くのがコツ。
🌿 補足:安全面で伝わりやすくする具体的なコツ
-
「通学距離(徒歩○分/自転車○分)」を数字で書く
-
危険箇所を地図で示したり、写真を添付する(審査担当者が理解しやすい)
-
「見守りが難しい時間帯」「雨天・積雪時」など、家庭の努力では防げない要素を説明する
💡教育委員会は「通学距離の長さ」よりも「危険を回避する合理性」を重視します。
“遠いから”ではなく、“安全に通える選択をしたい”という書き方が、誠実で印象の良い伝え方です。
学区外通学の理由を一生懸命書いても、実際に受理されなければ途方に暮れてしまいますよね。実際に通りやすかった理由、書き方のコツ、自治体ごとの傾向、都市部や地域別の特徴などをこちらで詳しくまとめています。↓
学区外通学理由まとめ。通りやすい、通りにくいケースと家庭で多い実例

.
まとめ|理由書は「家庭の現実」と「子どもの安心」を伝えるもの
学区外通学の理由書は、希望を通すための手紙ではなく、生活の現実を伝える公的文書です。
だからこそ、感情的にならず、淡々と「いまの暮らしに何が必要か」を書くことが大切。
どんな理由であっても、根底にあるのは「子どもの安心と安全を守りたい」という想い。
その想いが丁寧な言葉で伝われば、きっと誠実に受け止めてもらえます。
もし迷ったら、以下の3つのポイントを意識して書いてみてください。
✅ 最後に見直したい3つのポイント
-
事実を中心に書いているか(勤務時間・通院・通学距離など)
-
「家庭の都合」ではなく「子どもの生活リズム」を基準にしているか
-
丁寧で簡潔な言葉になっているか(長文・主観的な表現は避ける)
“誰かに読んでほしい誠実な文章”になっているかどうかが自然と分かります。
🔗 関連記事

.🕊 まとめ
学区外通学の理由書を書くとき、
「どうすれば通るか」より「どうすれば子どもが安心できるか」を考えることが、
いちばん大切な視点だと思います。
一枚の書類の向こうに、毎日を頑張る家庭の姿があります。
あなたの言葉で、その想いを丁寧に届けてくださいね。
※ここで紹介した内容は、実際の手続きをスムーズに進めるための一般的な例です。
自治体によって申請条件が異なりますので、詳細は各教育委員会にご相談くださいね。